- 選択肢の文章は、後半に不適当なことが書かれていることもあります。途中「これだ!」と思っても、必ず最後まで選択肢を読みましょう。
- 解答に迷ったら、状況設定や何が問われているのかをよく理解するように、もう一度問題文を読み直しましょう。
- 記述問題は、誤字・脱字などに注意して、読みやすい丁寧な字を書きましょう。
- 答案用紙を提出する前に、「適当」・「不適当」を間違えて答えていないか、解答漏れはないか最終チェックを!


「試験対策の方法が分からない」、「勉強の成果がなかなか出ない」など、独学の試験対策で困っている方はいませんか?
秘書検定対策講座を実施している早稲田ワーキングスクールの現役講師が、筆記試験対策のポイントを伝授します!
ぜひ参考にしてみてください。
まず、試験日から逆算して学習計画を立てましょう。その際、学習期間によって以下のような目標を立てると良いですよ!
※上記の学習期間はあくまで目安です。
では、各段階で試験対策のポイントを紹介します!
「マナー・接遇」や「技能」は、冠婚葬祭のマナーや封書の表書きなど、日常生活でなじみのある内容も出てきます。「必要とされる資質」から学習を始めても理解が深まらないときは、「マナー・接遇」や「技能」から取り組んでもOK!どんな順番でもいいので、まずはテキスト一冊をひと通り仕上げましょう。
テキストを読んである程度自信が付いたら、過去問題に取り組んでみましょう。問題を解いたら自己採点をして、領域ごとに正解数を出します。間違いの多かった領域があなたの苦手領域です。
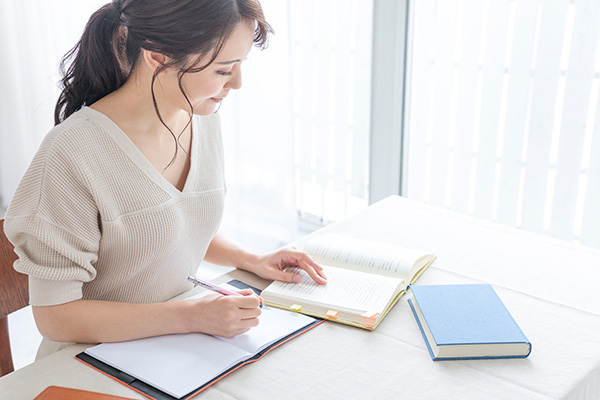
選択問題を解いた後の自己採点で、なぜその選択肢を選んだのか忘れてしまうことがあります。それを防ぐために、選択肢を選んだ理由を余白にメモしておきましょう。そうすれば、判断を間違えたところが分かるので対策を立てやすくなります。
記述問題が苦手という方は、解答例を書き写すなどして解答の仕方を覚えてから、自力で取り組む方法が効率的でオススメです。

得点を効率よく取るためには、苦手領域の克服が必須です。
まずはひと通り学習して、苦手な領域を見つけておきましょう!
過去問題を解いてみて、間違いが多かった領域から対策を始めます。
この2領域は、心構えや対応の仕方が問われる内容です。社会人の方は、自分の経験を基にして試験問題に向き合ってしまうことがあります。しかし、基準はあくまで秘書検定の審査基準ですので、解説までしっかりと読み込んで基準を″理解する″ように心がけましょう。
この領域は暗記領域です。出題された用語とその意味がつながるように覚えましょう。暗記カードを作り、通勤・通学などのスキマ時間を使って覚えるのも効果的ですよ!

この2領域はボリュームゾーンで、覚えることがたくさんあります。
内容を<暗記系>と<理解系>に分けてコツコツ取り組みましょう!
例えば、以下のようにカテゴリー分けします。

秘書検定の試験に出る問題は、ビジネスで活用できるものばかりです。社会人の方が業務に生かすことはもちろん、学生の方も先生や先輩など目上の人と接するときに、秘書検定で覚えたことを実践してみましょう。覚えたことをアウトプットすれば、学習効果が高まるだけでなく自分の印象もよくなって一石二鳥です。
本番ではイージーミスを防ぐためにも、見直しの時間確保は必須。すべての問題を1時間前後で解けるのが理想です。
間違えた問題は繰り返しチャレンジしましょう。合格のためには、不正解に向き合うことが欠かせません。
【一般知識】に出てくる用語や【マナー・接遇】【技能】の内容で″暗記系″にカテゴリー分けしたものは、″一つ覚えたら合格に一歩近づく″という気持ちでラストスパート!時間がない時でも用語ひとつでも覚えれば、やる気も上がります。

″暗記系″の内容で、どうしても覚えられないものがあれば、「替え歌」や「あいうえお作文風」で挑戦してみてはいかがでしょうか。
【替え歌の例】
~キラキラ星のメロディーで
賀寿を覚える~

【あいうえお作文風の例】
「秘扱い」

秘書検定の試験対策において、最初は間違えることが多く落ち込むかもしれません。
しかし、それは合格するために必要なステップです。落ち込まずに、問題が″解けた″という感覚をコツコツ積み重ねていきましょう。″分からない″から″分かる″ようになれば自信も付き、自分の成長も感じられるものです。
今回ご紹介した、内容を″暗記系″と″理解系″に分けて取り組む方法や替え歌などで覚える方法は、あくまでも学びのきっかけづくりにすぎません。そこから皆さんに合った学習方法を発見してもらえたらよいと思います。
皆さまの筆記試験合格を心よりお祈りいたします!

